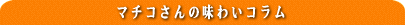 |
|
�������E���̐l�ɓ��{�̋��y�������Љ�邱�ƂɂȂ�����A�~�����ɂȂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B���{�̕��y�����~�����́A���ɂ̕ۑ��H�ł��B�ۑ������悯���100�N�O�̂��̂ł��H�ׂ���̂ł��B
�~�����ɂ̓N�G���_�̎_���������Ƃ����܂��B���̂����ς��~�������C���[�W���邾���Ō��̒��ɂ͑��t���\�\�B���̑��t�̕��傪�����z�����悭����Ƃ̂��ƁB�ŋ߂͔~�|�h�����N�Ȃǂ�����܂����A�������J�ɂ͍œK�B�����Ƃ��̂���a�C�ɂȂ�����A�����Ɣ~�����͒�ԃ��V�s�ł����ˁB
�ߐ{�����̂��������́A�~������Ђ���v���ł��B���ꂼ��̉Ƃň�������ɂȂ�̂���`�����邩��B�ߐ{�����ɕ�炵����l�́A�~�����Ђ��N�P��̍s���ɂ������ł��ˁB�V�[�Y���ɂȂ�Ɠ��̉w�ł��~�̐��������������Ă��܂���B
|
|
|
|
|
 �@�@ �@�@ |
 |
| (1) |
�~�c�c2�s |
| (2) |
���c�c400�� |
| (3) |
�����̗t�c�c2�� |
| (4) |
��(�����̗t�p)�c�c100�� |
| (5) |
�Ē��c�c�J�b�v1/2 |
|
 |
| ��≩�F���Ȃ����~���Ђ��ǂ� |
|
|
 |
| �����~�͈�ӁA���̒��ɐZ���ĊD�`���������܂��傤�B���F���Ȃ����~�͂��̂܂g���Ă����v�B�ւ������̂��Y�ꂸ�ɁB |
 |
| �~�ɏĒ�����������A��200�����܂Ԃ��܂��B |
|
 |
| �M���ŏ��ł����r��p�ӂ��āA�c��̉�200�����ӂ�Ȃ��~�����܂��B |
|
 |
| �d���̂��ĉ��Ђ����܂��B�͂��߂�2�s�̏d�B2���قǂŐ��C���ł���1�s�̏d�ɂ���B |
|
 |
| ���C����������̗t����100���ł��݂܂��B�D�`�͎̂Ă܂��傤�B���Ђ��łɂ��ݏo�Ă���`�J�b�v1��������ƐԂ����܂�܂��B |
 |
| ��������{�Ђ��B������r�̒��ɒЂ����Ă���~�̏�ɓ���܂��B |
 |
| 7�����{�A�Ђ����~�₵����3�����炢�����܂��B�e����ꏏ�ɏ��ł��܂��傤�B����ŁA�~�����̊����B |
 |
| ���������Ȃ��ƃJ�r�̌����ɂȂ�܂��A�ۑ������������̏ꏊ�͔����܂��傤�B |
|
 |
| �����܂Ԃ��ĒO�O�� |
 |
| ���炭����Ɣ~�|���o�� |
 |
| �����̗t�����݂܂��傤 |
 |
| �p���p���Ƃ܂��悤�� |
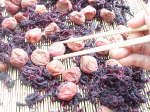 |
| �V�C�̗ǂ�����I��� |
|
|
|
|